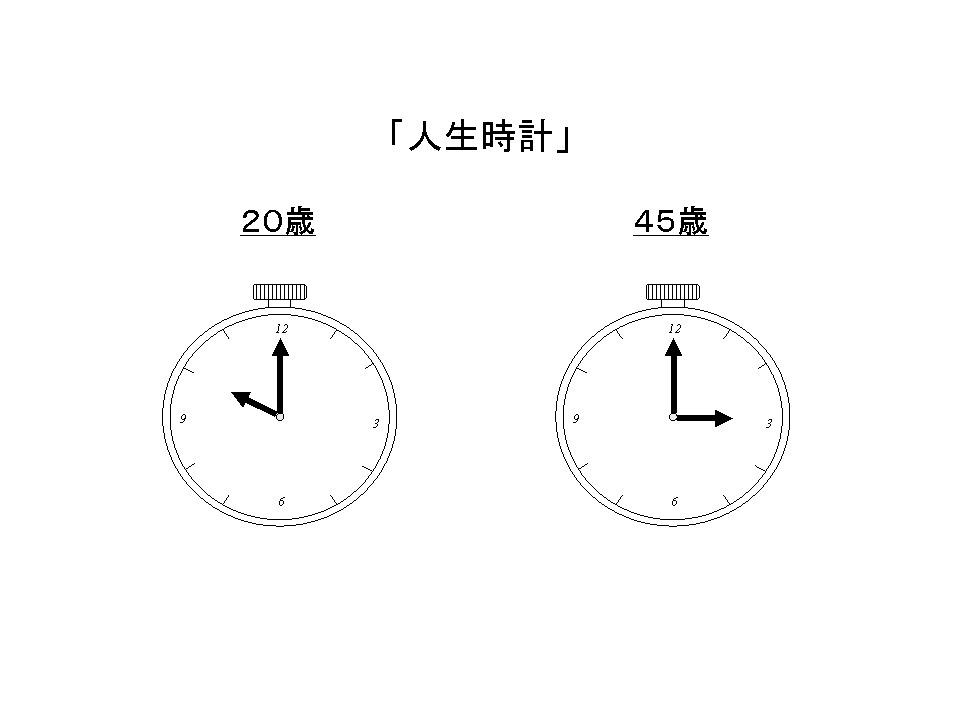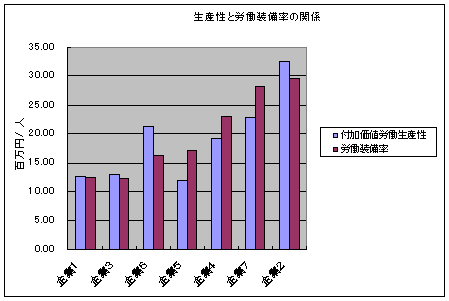考えるヒント(05)
豹のリーダーシップ、狼のリーダーシップ (2010/07/06)
桜の園、または道具としての組織論について (201004/14)
専門化と総合 - 組織戦略の二つの方法 (2010/04/07)
超入門・問題解決力 - 問題とは何か、課題とはどう違うか (2010/02/19)
時間の中に生きる(2010/01/04)
超入門・ビジネス英語 (2) 発音と息と意思疎通 (2009/08/02)
超入門・ビジネス英語 (2009/07/26)
目標、計画、ターゲット(3)-共通言語をつくろう (2009/06/17)
計画の二重帳簿はなぜ発生するか - 目標、計画、ターゲット(2)
(2009/06/09)
目標、計画、ターゲット (2009/06/02)
情報をデータにおとし込む (2009/03/15)
データを情報に変える (2009/02/15)
豹のリーダーシップ、狼のリーダーシップ
(2010/07/06)![]()
暑い日の昼下がり。豹たちがサバンナの樹の下で会議を開いている。
「おい。全員そろったか。」
「大体、そろいました。ただ、ジミーの奴が、遅れています。来る途中、灰色ウサギを見かけたとか言って、横道それて追いかけてきました。」
「またかよ、あいつは。つまんねぇ小物狙いするんじゃねえって、あれほど言ったのに。」
「あとは全員来ています。」
「よし。スタッフ・ミーティングを始めよう。乾期ももうそろそろ終わりだ。この頃だいぶん獲物も減ってきている。暑さで体力も消耗してる。だが、もう少しの辛抱だ。雨期になればガゼルの群れが川を渡って戻ってくるだろう。いいか! ここが勝負どこだ。」
「へい!」
「あいつら、大群になって川を渡る。そうすりゃワニも近寄りにくいからだ。だが、中には必ずガキを連れた奴らがいる。足手まといで、川を渡るのも遅くなる。狙い目はそこだ。渡りきって岸に上がる頃にはヘトヘトになってるはずだ。そこを樹上から一気に襲うんだ。」
「わかりました。」
「--ハァ、ハァ、遅れてすいません。」
「ジミーか。どうだったよ、戦果は?」
「いやあ、ウサギの奴、すばしっこくて。20分も追いかけましたが、最後は見失っちゃいました。」
「ざまぁねぇな。いいか。俺たちゃ、誇り高い豹だ! サバンナの勇者だぞ。大物を狙え。風下から、音を立てずに、一気にやるんだ。おいジミー、爪を見せてみろ。」
「・・へい。」
「何だこのヘボ爪は。木の幹で爪を磨くんだ! いいか、スピードと爪の鋭さが、仕事のカギだ。俺は一度しか言わねえぞ。お前たちも良く覚えておけ。じゃ、今日はこれで終わりにする」
「あの、リーダー。」
「何だ。」
「本社から、地区の今期の実績と、来期の目標を数値で挙げろって、指示が来てますが。」
「ちっ、本社の奴らと来たら! 自分じゃ何一つしねぇくせに、いちいち偉そうに言いやがる。今期の戦果ぁ? そんなもんいちいち覚えてられるか、しゃらくせえ。」
「でも何か答えませんと。」
「じゃあお前が適当に答えておけ。来期の目標も『ガゼルをたんまり』とでもな。あいつら、現場で走り回ったこともないくせに、数値目標だと? そんなもんお天道様だって知りゃあしねえさ。狩猟の仕事ってものには波があるんだ。」
「まったくです。」
「過去のことなんかいくらほじくり返したって、獲物が増える訳じゃない。俺たち豹はな、未来志向の生き物なんだ。誰かに“昨晩はどちらにいらしたの?”と聞かれても、“さあ。昔のことは忘れたぜ”--こう答えるんだ。」
「リーダー、それって『カサブランカ』のハンフリー・ボガードの台詞じゃ」
「馬鹿。古典からの引用、ってのを知らねえのか。教養のねえ奴らだ。この仕事、運がよけりゃ、大物にありつける。うまく仕留めたら、たらふく食って、あとはぐっすり眠るのよ。眠って、夢の中で、次の狩りの獲物のことを想う。これが俺たち豹の、未来計画ってもんなんだ。」・・・
同じ日の午後。狼たちが、岩の上で車座に這いつくばって、会議をしている。
「おい。全員そろったか。」
「ジョンがケガで休んでる以外は、皆そろいました。」
「よし。スタッフ・ミーティングを始める。議題は、今日と明日の狩りの配員だ。」
「はいっ。」
「乾期ももうそろそろ終わりだ。今年の乾期は長かったから、草を食い尽くした草食動物たちが、水を求めて上流の台地に移動してきているはずだ。お前たちも何か兆候を見なかったか?」
「そういえば、水牛と共生しているホロン鳥を、最近見かけました。」
「どこで何羽? もっと正確に言え。」
「一昨日、西側の台地で2羽。それから、昨日、南の森の入口でも3羽。」「こっちでも、二つ岩の上を4,5羽飛ぶのを今朝見ました。」
「よし。明らかに増えているな。良い知らせだ。他の者も、見たら正確に報告するんだ。やつらは数頭から数十頭で、まとまって行動する。だが、こういう移動時はしばしば、はぐれ野牛が出るもんだ。これを狙おう。」
「ラジャー。」
「西の台地の谷筋を狙う。皆で散開して、はぐれ野牛を探す。見つけたら、すぐに遠吠えで仲間を集める。1分以内に集まれるような距離を保て。野牛は警戒心が強い。すぐに近づかずに、遠巻きに包囲するんだ。いつもの隊形でいく。わかったな!」
「はっ。」
「7~8匹で相手を囲う。お前とお前、斜め後ろから威嚇して、野牛を谷の奥に追い詰めろ。両サイドは若手にやらせよう。ロン。フロントはお前に任せる。うまく相手を誘導しろよ。獲物が疲れて行き詰まったところを、俺がタイミングを決めて背後から飛びかかる。そしたら皆で一斉に攻撃だ。だが野牛は力が強いから気をつけろよ。とくに問題は角だ。去年、ビルが命を落としたのを覚えているだろ。」
「ハイ。」
「あのときのLessons Learnedは、うかつに野牛の顔の前に飛び出るなと言うことだ。低い位置から、後ろ足と首筋を攻撃する。今日はこれから、その練習に当てる。」
「あの、リーダー。」
「何だ。」
「本社から、地区の今期の実績と、来期の目標を数値で挙げろって、指示が来てますが。」
「乾期の成績は、大型動物 17頭、中型動物24頭、小型85頭、だったと思う。木の幹に牙で数を記録してあるから、一応確認してくれ。来期は、中型を30頭以上に増やして、大物への依存率を下げたい。そのためにも、もっと走るトレーニングが必要だ。だが気候変動で獲物が減るリスクはあるな。その場合のフォールバック・プランとしては、川向こうの地区と協力して、ガゼルの群れを狙うことも考えよう。」
「わかりました。そう報告しておきます。」
「いいか。俺たちの仕事はチームワークが命だ。抜け駆けは禁物だ。いつも言ってるから、耳にタコだろうが、あえて繰り返す。連絡を良くしろ。そして、経験したことは必ず覚えて、次に活かすんだ。」・・・
--あなたの組織は、豹のタイプだろうか、それとも狼だろうか? 組織のマネジメントには、いろいろなスタイルがある。おなじ会社の中でも、部門によって違うこともあるだろう。だが、この違いは、必ずしもリーダーの個人的資質だけで決まるものではないことに注意してほしい。
両者の一番の差は、「時間」の概念の差に現れる。あるいは、「記憶」と「予測」への固執と言ってもいい。
『猫の額』という言葉があるように、ネコ科の動物は前頭葉が小さい。これはどうやら、時間的な展望を持たずに暮らしていることを示すらしい。ネコは常に“今を生きる”タイプの動物なのだ。彼らは過去にとらわれず、未来のことを事細かく見通したりしない。獲物が目の前にあれば、一気に襲う。彼らは半夜行性の狩人で、とくに夜は視界が狭いので逃げられると追えない。その場で勝負をつけるしかないのだ。必然的に個人プレーで行動することになる(ネコは個人主義者だ)。そして成果は、個人的スキルと、獲物への遭遇機会とに大きく依存する。だから先など見通しても意味がないと言うことになる。
これに対してイヌ科の動物は集団で狩りをする(だから「一匹狼」は生存率が低い)。役割に応じた分業と、総合的判断に長けており、吠えによるコミュニケーションも発達している。社会的順位をつねに意識しており、獲物を食べる順序も厳格に決まっているという。相互扶助的だが、ある意味で軍隊的な息苦しい社会とも言える。ただ、組織的な仕事の成果は、個人のスキルにはあまり依存しないので、安定する。狩りが下手なものがいても、そこそこの結果が得られるのだ(豹の組織における成果は、個人の成果の合計にしかならない)。その分、予測も立てやすい。
どちらのやり方がベターなかは、仕事の特性によって決まると言っていい。ただし、一つだけ確実なことがある。もし、大勢で大きな仕事をしたかったら、狼型のやり方になるのは必然なのだ。猫は会社に向かないのである。
桜の園、または道具としての組織論について
(2010/04/14)
またや見む交野の御野の桜狩 花の雪散る春の曙 (藤原俊成)
古典歌人達が、「しづ心なく花の散るらん」とか「花にもの思う春は経にけり」と歌うとき、その「花」は桜のことを指すというのが約束だった。ただしそれは、薄緑の若葉とともに花を咲かせる山桜である。平安時代や鎌倉初期には、今で言うソメイヨシノはまだ無かったからだ。
サクランボは桜の樹になる果実のはずだが、桜の名所をどれだけ歩いても、初夏にサクランボを見つけることはない。それはソメイヨシノが交配でつくられた不稔性の桜だからだ。花は咲いても実は結ばないのである。この木は、基本的に接ぎ木で増やすので、遺伝的に言うならば、すべて同一である。そのため性質も均一で、一斉に花が咲いて一斉に散る。桜の木が一本だけ生えている姿は儚なげな情緒が漂うのに、たくさん並んでいるときは、かすかに不穏さのようなものを感じるのは、もしかしたらクローンの集団だからなのかもしれない。
接ぎ木とか挿し木といった繁殖法を見ると、植物というのは本当に不思議な生き物だと、ときどき思う。ジャガイモにトマトを接ぎ木して、地下と地上に別々の実りをもたらすことさえ、やろうと思えばできる。接ぎ木は、明らかに別の個体同士の接合なのに、一つの生き物にインテグレートされるのである。ゆっくり時間はかかるが、まさに「すり合わせ型」だ。
これに比べると、動物というのは構造がはっきりしている。蝶であれクジラであれ、羽が何枚とかヒレが一対とか構成が明確で、ブレがない。勝手に個体同士が接合することもない。人間ならば眼が2個、口は一つで、心臓が一個で腎臓は2個、足は2本といった具合に、「部品表」を書くことができる。各部品の機能は明確に決まっている。むろん血液や体液のやりとり、神経系や内分泌系の情報交換、温度や圧力の環境管理など、さまざまに複雑なインタフェースで他とつながっているが、部品と見なすことは可能だろう。
西洋人は対象を分析してこまかく分解していき、それで物事を理解し把握するアプローチが得意である。西洋医学の行き着く先が、部品としての臓器の移植や再生交換に至るのは当然かもしれない。彼らは身体というものを、モジュール構造のモノとして見たがる。だから故障したり古くなったりしたら、新品と取り替えるべきだとの発想にいくのだろう。つまり、体の器官というのは、道具なのである。だが、誰にとっての道具なのか。
彼らの身体観は、その延長としての「組織」観に無意識につながっているのではないかと感じるときがある。いつだったか、外資系の、若くて優秀な経営コンサルタントが、企業の組織に関する混線しがちな議論に割って入って、「でも組織形態は、経営目的を達するための道具じゃないですか!」と発言し、それを聞いた周りの人達が一瞬、しんと静まるという光景があった。会社員は皆、組織論が大好きである。誰もが自分の組織や立場を守ろうとする。次第次第に組織自体が自己目的化する。それを、「道具にすぎない」と断定する冷静さに、目を覚まされた思いをするのだろう。
M・ポーター流の『専門化』による競争戦略の行き着く先が、“個別機能に特化した組織がモジュールのように組み合わさって、新しい全体性を持ちうる組織アーキテクチャー”だと、前回書いた(「専門化と総合 - 組織戦略の二つの方法」 2010/04/06)。企業というのは、その業態に合わせて、だいたい似たような機能組織を持つようになる。人事部とか財務部とか資材部、物流部、技術部、製造部、情報システム部といった風に。これらの機能部門が、会社組織を成り立たせる「部品」である訳だ。そうなると、陳腐化した部品、機能の低下した非効率な部品ははずして、新しく高機能な、かつランニング・コストの小さな部品に取り替えよう、との発想に至るのも必然である。
この流れにしたがって起きた現象が、アウトソーシングであった。物流機能の3PLへの移管、情報システム部門の独立化や売却、福利厚生の外部利用化などは、その典型である。それに続いて起こっているのが、工場の製造子会社化、ならびにEMS(製造受託会社)への移管であろう。“うちの工場は高コスト体質でかなわん。海外の安い会社に作らせたらいいやないか”という訳である。こうして「グローバル化推進」のかけ声とともに、中国生産がブームになり、インドネシアやベトナム生産がその後を追うことになった。設計(とくに詳細設計)を外部に出すことも広まりつつある。
しかし、本当にこれら機能部門はアウトソース可能なのだろうか。私が提起しているのは、「アウトソースすべきかどうか」の是非論ではなく、「可能かどうか」の技術論である。欧米流のモジュール型組織アーキテクチャーが可能であるための条件は、はっきりしている。それは『個別機能のインタフェースが明確に規定され標準化されている』ことだ。そうでなければ、それはモジュールにはならない。標準インタフェースが存在しなければ、それは「すり合わせ型」部品だと考えられる。
そこで、読者諸賢に一つ質問したい。皆さんは、現在たずさわっておられる職務について、職務記述書(Job
description)をお持ちだろうか? また、現在の業務について、ワーク・パッケージのインプット・アウトプット・使用ツール等を規定した定義書は、お持ちだろうか。
私自身の経験でいえば、フランスの企業との合弁事業で働いていたとき、人を新たに雇う場合は職務記述書の作成が、まず第一に要求された。だが、日本の本社では職務記述書など見たことがない。私の勤務先はエンジニアリング会社なので、さすがにWBSとワーク・パッケージの標準は一応規定している。が、プロジェクトごとに例外も多い。中間管理職としての日々の業務は、その例外との戦いみたいなものだ。
ISO9000の品質マネジメントシステムを持っている企業は、業務フローの記述をまとめているはずだが、その規定は運用上の裁量範囲(いいかえれば曖昧さ)を残している場合が多い。つまり、日本企業の実態としては、「すり合わせ型」の組織アーキテクチャーが主流なのではないか。
こうしたすり合わせ型の組織で、ある機能部門だけをモジュール部品として交換しようとしたら、どうなるか。機能不全の、木に竹を接ぐ結果になるのは火を見るより明らかである。にもかかわらず、こうした『組織戦略』が流行しているのは、欧米流のマネジメント思想を、自分の立脚する環境を見ずに、直輸入して実行しようとするからであろう。
それは、働く個々人についても同様である。製造部門の直庸を派遣工に取り替える。設計者も外注に切り替える。満足な職務記述書も用意せずに。その結果、従来は現場の工夫で押さえ込んでいた問題が、つぎつぎに表面化してくる。管理スタッフの負荷がどんどん増えていく。
だったら職務記述書や業務標準定義書を充実していけばいい--これは一つの解決方向であろう。ただし、組織のアーキテクチャーは、製品アーキテクチャーや、サプライチェーンの方向性と、微妙に、しかし密接に関連していることを思い出してほしい。すり合わせ型の製品アーキテクチャーは、プル型のリーンな供給指示に結びついており、モジュラー型製品は在庫をもつプッシュ型供給指示が便利である。では、個別仕様部品の多い、すり合わせ型製品で、設計や購買の業務標準定義書を簡単にかけるだろうか。書くためには、バリエーション・リダクションやGT化といった、相当高度な工夫が必要なはずである。
組織は経営の道具にすぎない、というテーゼは明瞭で、分かりやすい。専門化にもとづく組織アーキテクチャーは、何となくカッコいい。だが、分かりやすさや格好良さだけで、複雑な物事を決めることはできない。周りがみんなそうするから、といって行動するのでは、実を結ぶことのない桜の園のクローン集団と同じになってしまう。まして何も捨てない「総合」型組織アーキテクチャーで道具論を振り回したら、滑稽なだけではないか。
私は「すり合わせ型」が良いか「モジュラー型」が良いか、二者択一の議論をするつもりはない。あるいは、組織論には第三の道を探るべきなのかもしれない。そもそも、会社を構成する人々は、会社の道具だろうか。そして私の身体は私の道具だろうか? それを考える基準とは「何か」を、もう一度問いたいのである。
専門化と総合 - 組織戦略の二つの方法
(2010/04/07)
もう10年以上前のことだが、SAP社の開催するユーザ・コンファレンス「SAPPHIREジャパン」が、横浜のみなとみらいで開催された時、マイケル・ポーター教授の講演を聴きにいったことがある。ご存じと思うが、ポーターは「競争優位戦略」とか「バリューチェーン」の概念提唱で有名な経営学者である。
その講演でポーター教授は、日本企業と韓国企業を、よく似た欠点を持つ、と言って叱った。わが国では昨今、官民を挙げて日本企業と韓国企業との優劣比較がお盛んだが、彼の目には、両者は共通に見えたのだ。
その共通の欠点とは何か。それは「総合」という名前の、切り捨て戦略の無さである--そう、ポーター教授は断じた。これが、両国企業の安定した成長を阻害しているのだ、と。
彼の主張を理解するためには、その前に少し知っておくべき事項がある。彼の学説の依って立つ根拠である。そもそもポーターは、経済学の若き俊英として出発した。彼の若き頃、経済学は完全自由市場における理論的性質について、さかんに研究していた。それによると、市場が完全競争の状態に近いほど市場成果が良くなる、と考えられている。つまり、売り手と買い手が多数存在し、参入が自由に行われ、取引される商品が均質で、取引主体が情報を完全に有している状態では、資源配分が「効率的」に行われることが証明される。経済学で「効率的」というのは、いいかえれば売り手(企業)が過剰な利益を占有できず、消費者に還元されている状態をいう。
経営学の研究分野に進出したポーターは、この証明を逆手にとって、考えた。企業が収益性を安定的に高めるためには、完全競争の市場を避ける必要がある。「効率的な」市場ではなく、あまり競争のない市場や、あるいは競争程度の低い状況を創出するべきである--彼はそう議論を進めた。逆転の発想である。
ポーターによると、市場の競争状態は、(1)新規参入、(2)代替品の脅威、(3)買い手の交渉力、(4)売り手の交渉力、(5)既存企業間の競争程度、によって規定される。そして、競争状態が分かると、その産業に属する企業の平均的な収益率が予測できる。さらに彼は、企業が競争優位な立場に立つための一般的戦略として、
・コストリーダーシップ戦略
・差別化戦略
・集中戦略
の3つをあげるのである。しかし、この話は「企業戦略論」の教科書や入門書にいくらでも書いてあるので、ここでは深入りしない。
こうした理論を説明するかわりに、ポーター教授は、見事な戦略を実行している企業の例を講演であげた。忘れもしない。そのとき彼があげたのは、IKEAとNeutrogenaとSouthwest
Airlinesであった。
IKEAについては、どんなビジネスモデルの企業か、すでに知っている人が多いだろう。ニュートロジーナは、無香料・無添加の石鹸で女性に知られた企業である。ニュートロジーナは肌に対する刺激がとても少ない。その特徴を、同社は、皮膚科の専門医にサンプル試供品を無料で配布する事によって、消費者に知らせた。肌荒れに悩む女性に、皮膚科の医師が“試しにしばらく使ってみたら”といって渡す。その効果を知った患者は、それをずっと使い続ける。こうして、ニュートロジーナ社は、ドラッグストアの店頭に山積みされる石鹸の安売り競争に巻き込まれることなく、自社の価格を維持し続けたのである(現在はohnson
& Johnsonに買収された)。
Southwest航空を知っている日本人は少ないかもしれない。だが、巨大航空会社がひしめく米国航空産業において、同社は特別の地位を占めている。Southwestは、中小規模の都市を結んで飛んでいる。大都市では、わざわざサブの小さな空港に就航する。日本でたとえていえば、千歳空港ではなく札幌丘珠空港に飛んでいるようなものだ。
Southwestは、原則として手荷物だけで、スーツケースなどの荷物預かり(check-in)サービスをしない。そのおかげで、旅客はすっと空港に行って、すっと乗り降りできる。また飛行機も定時に離発着できる。機が遅れたり、時間変更したりするときの最大の問題が、あずけた荷物だからである。
Southwestはまた、どこの路線でも、極力同じ種類・同じサイズの機体を運行する。路線によってジャンボを飛ばしたり747にしたりといった使い分けをしない。これは、機体のメンテナンスや、いざというときの機体繰りを簡単にするためである。
こうしてSouthwestは、顧客満足を確保しながら、できるかぎり他の航空会社との競争に巻き込まれないようにしてきた。だから同社だけは、長い間安定して利益を稼ぎ続ける事ができたのだ。収益を上げたければ、価格競争は避けろ。誰もが参入する、利幅の薄いムダな事業は捨てて、集中しろ。競争を避けるところに、競争戦略はある。これが、ポーター教授の説明であった。
ひるがえって、日韓の企業はどうか。この二つの国では、企業が大きくなればなるほど、「総合」と称していろいろな市場に手を広げる。その結果、どこに特色がありどんな哲学があるのか不明な大企業ばかりになっていく。何も捨てない。「何かを選ぶとは、それ以外のすべてを捨てる事だ」とポーターはいう。したがって、何も捨てない企業には、何の戦略もないのだ、と彼は断定する。
彼の講演を聴いた帰り道、歩きながら考えた。たしかに指摘は当たってる。○○建設とか、○○重工とか、○○電子、○○製作所といった企業名(空欄は好きな漢字やハングルで埋めてください)を想起させる。そして、くやしいことに、自分の勤務先も『総合エンジニアリング』を標榜しているのだった。
捨てる事には、勇気がいる。撤退には、事実とてもエネルギーがかかる。だから、難しい。とはいえ、何にでも手を出したがる「総合」志向は、また同時に、捨てられない、賭をできない、リスクをテークできない「三ない」思考でもある。戦略や仮説をもてない。したがって、「決めない人々」で社内はあふれかえる事になる。総合企業が沢山ある社会では、皆が同じ事業に参入したがる。だから必然的に過当競争に向かっていく。
もちろんアメリカにだって総合巨大企業は沢山あり、大儲けしたり大損したりしている。そんなことはポーターも百も承知だ。だが、彼はたぶんSouthwestのような、ビジネスモデルの設計思想が明確で、はっきりした戦略に賭けるタイプの企業が好きなのだろう。設計思想とは見切りだ、と以前このサイトにも書いた(「私はまだDOSアプリを使っている」)。何もかも製品に詰め込む事はできない。だから、何を取って何を捨てるかが、設計の思想なのだ。
ポーターの論理に従うと、必然的に組織は専門化の方向に向かう。何でもできる、何でもやりたがる総合化の組織ではなく、これだけしかしない、これだけは誰にも負けない、そういう組織に。そして、そういう個別機能に特化した組織がモジュールのように組み合わさって、新しい全体性を持ちうるというのが、この論理の先に待ち構えている組織アーキテクチャーだということになる。
こうして、専門化と総合という二つの方法は、「プッシュとプル - サプライチェーンの二つの方法」や、「モジュラーとインテグラル - 製品アーキテクチャーの二つの方法」につながっていく。だが、いつものくせで、長くなりすぎたようだ。この話の続きは、稿をあらためて、また書こう。
超入門・問題解決力 - 問題とは何か、課題とはどう違うか
(2010/02/19)
Kさん、おたより楽しく読ませていただきました。この混沌とした時世に、それでも何か光るブレイクスルーが(あるいは、お言葉を借りれば「ブレイクスルーの予感が」)感じられるのは、何より心強いことです。
確かに、私たちの生きている時代は、課題だらけです。日本は『経済一流、政治三流』などと威張っていられたのは過去のこと。お偉方の頭の中では、いまでも産業技術では世界トップと思われているのかもしれませんが、実務家の日々の仕事で見えてくる姿は、だいぶん擦り切れてくたびれかけた「超一流」、品質も技術も物流も販売も、困難をかかえて制度疲労しているように思えます。
それでも、日本の製造業を訪問するたびに感じるのは、そこに働く人たちの優秀さと誠実さでしょう。この底力をうまく活かせれば、まだいろいろな可能性があるのだなと、御社のチャレンジを見て思います。ただ、そこでいつも障害となるのは、組織のマネジメント力の弱さ、意志決定の遅さ、そしてKさんのおっしゃる「問題解決力」の不足でしょう。
これは、縦割りの機能型組織だけで業務を回してきた製造業が、新しいことに挑戦する時に、典型的に現れるようです。各人、持ち場で最善を尽くす--それは得意です。しかし複数部門にまたがる課題が発生した時は、それを解決できないまま、「様子見」と「判断の先送り」だけで時間を浪費してしまう。Kさんが、新サービスの上市期間(Time
to Market)について、アジアのライバル企業に先を越されないかと心配されている理由は、この点にあると思います。
それを乗り越えるために、「課題管理表」をつくり、関係者間で共有されるというアイデアには、私も賛成です。解決しなければならない項目をはっきりさせて、皆で共通認識すること。そして解決のオーナーシップ(つまり担当者)を決めて、期待すべき解決の期日を設定し、対策と最新状況を表に書くこと。これはまさにプロジェクト・マネジメントの第一歩であり、機能型組織の壁を越えたクロス・ファンクショナルな取り組みの開始だとも言えるでしょう。
ただ--Kさんには「またか」と言われそうですが--私には一点、気になることがあります。Kさんは「問題」と表現されたり「課題」とおっしゃったりしておられますが、課題と問題はどこが違うか、ご存じですか? この二つは、違うのです。なので、課題解決と問題解決には、別の方法が必要なのです。
「問題とは何か」--まあ、こんな変な問題を言い出すのは、私ぐらいかもしれません(笑)。課題とは問題を、ちょっとかっこつけて言い直しただけだ。現場で「問題」と泥くさく呼ぶことを、役員会議室の中では「課題」と称する。そんな風に思っている人も、多いと想像します。ですが、試しに英語でどういうか、考えてみてください。問題は"issue"とか、"problem"ですよね。では、課題は? "assignment"とか"challenge"、ないし"task"になるでしょう。「解決する」はsolveとかresolveですが、課題解決を"assignment
solutions"とは、まず言いません(これではまるで数学の宿題の解答みたいです)。
課題とは、能動的なものです。“あるべき姿”を思い描いて、現実をそこに向かって変えていくためのポイント--これが課題です。コンサルタント風の言い方をすると、"To-be"と"As-is"の間のギャップを詰めていく作業が「課題」なのですね。これを解決するためには、まず“あるべき理想像”を明らかにしなければなりません。つまり非常に意識的で自覚した活動だ、ということがお分かりいただけると思います。
ところが、「問題」は違います。問題とは、(意識的にであれ無意識であれ)“期待していた状況”と、現実の状況のギャップを指します。「今期の売上げが問題だ」という時、それは「今期の売上げは期待していたほどは上がりそうもない」という悩みを指すわけです。客先が品質にクレームしてきた--これは、“客先はクレームしない”という無意識の期待、当然こうだろうという「思い込み」がつくり出した問題なのです。
ということは、どうなるでしょうか。問題は、外から割り込んでくる障害で、受動的なものだと皆が考えている。しかし、本当は、無意識に持っていた「期待の質」がつくり出したものなのです。だから、一つつぶしても、きっとまた別の問題が浮かび上がってきます。なぜなら、「期待の質」が変わっていないからです。そして、最も困る期待とは、「何も変化しないはずだ」という期待なのです。
日本が一人あたりGDPで中国に抜かれるのが問題だ、と言う人は、無意識に、日本は当然2位であり続けるはずだ、と信じている。どうしてそう信じられるのか、私には分かりません。それよりは、日本で雇用が十分生まれるには、どの程度のDGPで「あるべき」なのかを考えた方が、生産的なように思えます。失業問題は、たしかに「問題」です。まともな人は、まともに暮らせるべきだ、というのは当然の期待ですから。
Kさん。『問題解決力』に類する本は、書店に行って企画広告やビジネス書のコーナーにいけば、いくらでも見つかります。私は、そこに書いてあるような手法論を、いまさらご説明しようとは思いません。問題解決に本当に必要なのは、どのような視点・視野から問題を設定したのか、というスタンスです。たいていの場合、問題設定のスタンス自体を間違えている。
典型的な例が、トレードオフに関連する問題です。在庫は減らしたい。でもリードタイムは短縮したい。二つの漠然とした期待があるが、その間にトレードオフが生じているのです。こういう時、部門の都合でどちらかの問題だけを「解決」するのは簡単です。でも、もしかしたら、部品消費量を見直すサイクルを半期から月単位に短縮する、ということが「あるべき姿」なのかもしれません。だとしたら、目の前の問題解決は、ちっとも課題解決に近づいていないのです。
優秀な人ほど、自分の得意とする技術領域に持ち込んで「問題」を解決しようとする傾向があります。製造コストが問題だというと、機械屋は設計で、システム屋はソフトウェアで、物流マンはマテハンで解決したがる。しかし、本当に製造コストが問題なのか? 製造コストが低ければ販売競争に勝てるはずという、無意識の期待の方がまちがっていないのか? あるべき姿は、本当は何なのか--そのための課題を、最初にきちんと設定していたのか・・・
問題は生まれてくるもの。課題は生み出すものです。Kさんの課題管理表が、真の意味の「課題管理表」になって、取り組まれている新サービスが一日も早く市場に出てこられることを心から「期待」しております。
久しぶりに、自著『時間管理術』を読み直してみた。古い友人から、「偶然手に取ってみたら案外面白かった」とメールをもらったからだ。そして、おかしなことだが、自分でも案外面白かった(笑)。この本を書いてから3年経つが、中心となるアイデアや技法は無論すべて覚えているものの、ストーリーづくりや話法はけっこう忘れていたからだ。まあ、本の著者なんて案外こんなものである。
自分が読んだら面白いだろうなと感じるような本を書きたい、といつも思っている。共著・編著を含めたら1ダース以上の本を出してきたが、うまく書けたかどうかは、時間をおいて読み直してみるとよく分かる。時間をはさむと、自分はいつも少しだけ他人になるからだ。
私たちは忘れる能力を持っている。嫌なことも、良いことも忘れていく。もちろん、私たちは記憶し続ける能力だって持ち合わせている。それがあるから、一人の人格として継続性を持ちうるのだ。もし一晩寝て起きるたびに、直近の過去のことを一切忘れていたら、私たちはアイデンティティ=自分が誰であるか、を持ち得ないだろう。そんなSFじみた世界では誰も、魂の不滅、なんて宗教的な問題は考えるまい。自分が誰なのか、考える手がかりもないのだから。記憶の連続性こそ私たちの自我の骨格を形作っている。まれに脳の損傷などで長期記憶をもてない人が医学的記録に出てくるが、こうした人も、若い頃の記憶だけは保っていて、だから人格として成立しているのである。
しかし、すべての出来事をずっと記憶し続ける能力があったら、どうなるか。便利だと思う反面、つらい体験や恥ずかしい失敗もすべてリアルに覚え続けているのは、かなり苦痛だろう。なにより、すべての過去が強弱なく同等にならんでいる心的世界では、個性や特徴も生まれてこないにちがいない。記憶の濃淡やめりはりがあって、はじめて意見や好みも出来上がるのである。記憶の濃淡とはつまり、大事なことを覚え、大事でないことは適度に忘れることを意味する。適度な記憶の連続性と、適度に忘れる能力。こうして私たちは自分をとりまく世界に構造や意味を与え、適応していく柔軟性を獲得するのだ。
『時間管理術』のエピローグでは、自分のキャリア・パスのスケジューリングについて悩む若い質問者を登場させた。仕事を続けてキャリアを磨きたい。しかし留学してもっと勉強もしてみたい。留学がキャリアの断絶を意味するなら、早いうちが良いのかもっと後が良いのか、という問いかけである。女性ならばさらに、出産や介護といった事象もキャリアの蓄積に対するリスクとなりうる(この部分の記述は、日経文庫の編集者が慎重を期して、周囲の女性に問題ないかどうかレビューをしてもらった)。
これに対して、タイム・マネジメントの解説役であるY氏(主人公S君の叔父で、引退したコンサルタント)は、こう答える。「それを決めるためには、仕事の面から見た人生の目標と、自分に与えられた時間や境遇の制約を考えなくてはなりません」--これは無論、タイム・マネジメントの一般的な方程式である。その“与えられた時間”をイメージするために、彼は『人生時計』を紹介する。
『人生時計』というのは、0歳の誕生が朝6時に相当し、10歳が朝の8時、20歳が午前10時という風に、10年を2時間刻みで換算した時計である。45歳が、人生の午後3時を示し、90歳で、深夜零時にいたる。1年が12分、1月が1分、12時間でほぼ1秒に相当する。今、自分の年齢が何時何分にあたるかを考え、引退までの時間の長さと、キャリア・パスを考えてみるのである。何十年もの時間を想像するのはむずかしいが、時計の文字盤ならばイメージがわく。そして1、2年のキャリア中断は、10分か20分ほど席を外す程度にしか相当しないのだから、あせらずに大局から計画を立てなさい、とY氏は説明するのである。
この人生時計は一応私の創案だが、似たようなことを考えた人は他にもいると思う。『時間管理術』を読んだ人から、「ギクリとしました」と感想をもらうこともあった。たいてい私たちは、こうした大局観を忘れているからである。なぜ忘れるのか。それは「忘れる能力」のためではない。実は忙しすぎて、考える時間がないからである。仕事も確かに大事だろうが、自分のキャリア・パスを考えることはもっとずっと重要なはずである。それなのに私たちは毎日、“緊急だが重要でないこと”に追われて、“緊急でないが重要なこと”を考えるゆとりをとれなくなっている。
時間管理術の最終的な目的は、考える時間を確保することにある。考えている時間とは、傍から見ると、「何もしていないように見える時間」である。現代社会にビルトインされている様々な“時間どろぼう”(ミヒャエル・エンデの小説「モモ」の登場人物)が、私たちの考える時間を、片端から奪っていってしまうのだ。
私たちは時々立ち止まって、手を休めて、考える必要がある。大事なことを記憶し、大事でないことは忘れて、頭を整理するための時間である。そういう意味のことを、「静寂の価値」でも、「睡眠時間の必要」でも、「エントロピーを下げる」でも、「パンのみに生きるにあらず」でも、私は本サイトで折にふれて繰り返してきたように思う。でも、もう一度書こう。私たちには、考える時間が必要なのだ。
超入門・ビジネス英語 (2) 発音と息と意思疎通
(2009/08/02)![]()
さて、三番目の原則は簡単です。それは音声言語としての英語に関するもので、英語には腹式呼吸による息の強さが必要だ、ということです。
地下鉄に乗っていると、車両の騒音のために、すぐ隣の人の話し声もよく聞こえないのに、向かい側に乗っている英米人の会話の声だけは耳に入ってきた、という経験はありませんか? これは日本だけの現象ではなく、たとえばパリの地下鉄などに乗っていても、同じような経験があります。なぜでしょうか。格別、英米人は声の大きな人ばかりなのでしょうか。
それは、息の量に支えられた声の強さ、とりわけ子音の強さがもたらす結果です。ここは、音声言語としての日本語との大きな違いです。英語の発音では、なによりも子音(とくに破裂音や摩擦音)の明瞭さが求められます。英語では、子音は母音と母音の間に割り込んで分断し、音のブロックを作ります。そのブロックのつながりが語と文を作るのです。いわば、連結器でつながれた車両の列からなる列車かバスのようなものです。
ところが、日本語はそういう風に発音しません。ちょっと注意すればわかると思いますが、普通の会話をするにあたって、まず腹の底まで息を吸い込んでからはじめる人は希で、通常は肺活量の3分の1くらいの息でしゃべります。息のスピードは穏やかでゆるく、したがって摩擦音や破裂音も、母音の流れを完全にせき止めるのではなく、せいぜいその方向を変える程度の役割しかしません。日本語の音声は、いわば悠々と流れる母音の川のようなものであって、子音は両岸の岩のようにその向きを変えるきっかけなのです。口や舌の形はあまり大げさに動かさない。その結果として、やわらかく、ないし、ぼそぼそと聞こえる。これは地声の大きさの違いではなく、子音に込められる息の量の違いである、というのが私の考えです。
インド人の英語を聞いたことがありますか。母音はアイウエオ風で、かつ独特のイントネーションがあり、我々にはあまり上手には聞こえませんね。でも、ネイティブにとっては、日本人よりインド人の方が聞き取りやすいようです。その理由は、子音の勢いと強さにあると考えられます。
息というのは身体の動きで、無意識の習慣の世界に属します。日本語の息の体勢になれた私たちが英語の子音を明確に発声するためには、腹式呼吸に頼るしかない。そして、それを無意識の習慣に持ち込むまで、繰り返し練習が必要だ、というのが私の経験です。
第三の原則です:
「英語を話すときは腹式呼吸で子音に強さを与えろ」
さて、第四の原則ですが、これが微妙で、伝達するのが難しい。それは、言語の目的と自他の区別に関することで、日米両文化の最深層にかかわる問題だからです。
まず、英語は、「言語は意思伝達の主要な手段である」という明確なテーゼの上に立っています。そんなの当たり前じゃないか、とおっしゃるかもしれません。では、日本語の世界は、「言語は意思伝達の主要な手段である」という前提の上に運用されていますか。以心伝心、問わず語り、阿吽の呼吸が最上とされていませんか?
私の若い頃、世界的スターだったデビッド・ボウイという英国人ロック歌手が来日して、雑誌のインタビューで、こう発言しました。「言葉とは、コミュニケーションのための最も不確実な手段である。」--これは、おおかたの日本人読者なら、まあ同意するでしょう。しかし、これは英語の世界では、あり得ないほど非常識な挑発的・逆説的発言なのです。それをあえて言うのがボウイという人の立ち位置だったのでしょう。彼は視覚とかリズムとか身体的メッセージが、言語に勝るとも劣らぬ重要なメディアである、と考えていたわけです。
英語の発想の根底には、自己と他者を区別する感覚があります。自己と非・自己の区別、ではありません。そんなことなら、幼児期を卒業すれば誰もが身につけます。また、ウチとヨソの区別、でもありません。これは日本語世界の発想であって、自分の所属する集団(ウチの会社)と、それ以外の人々(ヨソの連中)の区別です。英語ではまず、主語としての大文字の"I"がある。そして、意志を持つ相手としての"you"がある。この両者は別の人間、優劣はあれども対等な別の個人であって、互いに意志も了解事項も異なっている。その間を橋渡しする、ほぼ唯一無二の手段として、言語がある。
だから、英語では、相手が理解できるように、発信者側が努力する責任を負います。無言の共通の了解事項(これをcontextというのですが)は最小限であるため、あらゆることは明確に、specificに表現する必要がある。同じ家族だろうが、同じ排他的クラブ員同志だろうが、この原則は徹底します。
日本語は、あまり輪郭のきつい、生々しい表現は歓迎されません。そこで形容詞を使って「先日は大勢の方が集まって」「大したものはございませんが」「それなりの評価をいただきました」といいます。ところが英語では、具体的で客観的を良しとします。「先週の水曜日には270人が参加して」「トップクラスの料理を用意しました」「85%の顧客がAランクと評価しました」・・こういうのが、英語に求められる表現です。
そして、何よりも互いの意志ははっきりと表現しなければなりません。「・・は難しいと思います」(I
think it is difficult to …)というのは断りの意思表示にはなりません(よほど相手が日本人相手の経験を持っていれば別ですが)。断りたければ、「我々は・・したくない」と言わなければなりません。日本人は"Yes,
but"というセリフが得意だと、よく言われます。これは、意見対立を回避すべきであるという日本語の運用原則が生む現象です。一方、英語は事実本位なので、YesはYes、NoはNo。意志の対立という事実があったら、まずそれをテーブルにのせます。そして、さて、じゃあそのGapをどうやって詰めていこうか、という話になるのです。
会話の雰囲気を保ちたいが為に、内心は納得していなくても、にっこり笑顔で"Yes, yes"などと言うと、後で「お前はあのとき"yes"と言ったではないか。あれは嘘だったのか」と反撃されてしまいます。英語は事実本位なので、逆に「嘘つき」"Liar"は最大の罵倒になります。英米人に面と向かって冗談のつもりでliarなどと言おうものなら、泥棒呼ばわり以上に、喧嘩になるでしょう。「嘘も方便」という日本人の価値観とは大違いです。社交辞令とか誇大広告とかは日英どちらの世界にも蔓延していますが、その位置づけが違うのです。
少し話がずれてしまいましたが、第四の、そして最大の原則です。
「英語とは、自他を明快に区別した上で、言葉こそ事実本位に意思疎通を行うための最上の手段である、との発想の上に立って運用される」
これは運用原則です。やろうと思えば英語でだって、いくらでも曖昧模糊とした会話はできます。しかし、それは英語らしくない。英語らしくない英語を、いくら明瞭な息と発音で話そうとも、ニセモノでしかありません。
Kさん。多くの白人社会では、本物とニセモノは峻別されます。ニセモノは、かりに憐れまれ、笑って許されているようでも、裏では軽蔑され拒絶されるのです。このご返事を書きながら、私自身、なんだか本物からどんどん遠ざかってきているのではないかと、反省の気持ちが増してきました。もう少し基本に戻って、ぜひ学びなおしたいと思います。Kさんも、どうか上の四原則をしっかりと理解いただいた上で、ぜひ有益なる意思疎通を行われることを願ってやみません。
(追伸:私は若い頃、中津燎子という人の「なんで英語やるの
」を読んで大きな影響を受けました。上に掲げた4原則も、本書の冒頭に書かれている原則を、私なりの経験を通じて咀嚼し言いかえたものです。賛否の大論争を巻き起こした本ですが、興味があれば読まれることをおすすめします)
Kさん。お久しぶりです。それにしても、今度のご質問には驚きました。EMS・受託生産の交渉について、というメールの表題から、てっきりまた生産管理に関する問題かと思いきや、何と英語についてのお悩みとは。
しかも、えー、率直に申し上げて、「ビジネス英語の上達法」なんて私の方が知りたいくらいですよ。仕事柄、私は毎日英語をしゃべり、英語の仕様書やレターを書いたりしていますが、自分ではけっして英語がうまいと思ったことはありませんし、仕事に十分なレベルに達したと考えたこともありません。
しかし、ご質問の主旨は痛いほどよく分かります。じつは、貴メールは、出張先のサウジアラビアのホテルで受け取りました(通信事情のため、ご返事は帰国後になりましたが)。それも、英語によるプレゼンテーションや交渉の能力の低さに、自分ながらイライラしながら宿に戻ったところだったからです。むろん、私のシチュエーションと、Kさんの状況は全くちがうとは思います。が、ここでは自省を込めて、私が知っている範囲のことをお話ししましょう。
ただ、具体的な語法のあれこれをお話ししても、きりがありませんので、ここでは英語を勉強するにあたって了解しておくべき原則、「メタ勉強法」とでもいうべき4つの原則をご紹介したいと思います。
まず、私自身の体験から申しますが、英語が一番うまくなったのは、会話学校でもなく、旅行や研修でもなく、直接ネイティブの相手とビジネスをするようになったときです。このとき、すでに30代の後半になっていました(ですから、別に外国語は20代でなければダメ、とあきらめる必要はないと思います)。とにかく言語において、必要は上達の母です。
ことに大事な条件として、「相手がネイティブであること」かつ「ビジネスの交渉が伴うこと」があげられます。英米人のNative
speakerは、一般に容赦がありません。英語で場に参加した以上、英語ができるはずだ、という前提に立っています(当然ですが)。おまけにネイティブの人は、外国語として英語を話す人々に比べ、圧倒的に表現力の豊穣さがあります。ついて行くのも大変ですが、学ぶ点も多い。極言すれば、Non-native同志で英語をいくら話していても、ほとんど上達は望めない、とさえ思います。
くわえて大事な点が、「ビジネスの交渉」であること。つまり、一言でも聞き漏らしたり言い間違えたりすれば、すぐにしっぺ返しがきて、その結果が自分の立場や評定にまで影響すること。こうなると真剣さが違います。外国語の習得においては、どれだけ集中してその言語情報を身に浴びるか、いわばその集中被曝量累積値がものをいうのです。ところが、たとえば旅行とか研修とか留学とかでは、相手も理解を手助けしてくれるし、自分の給料に響く真剣さも足りません。まして、ガールフレンドとつきあうなんて何の語学の足しにもならないでしょう。言葉なんか分からなくたって通じ合う世界ですから。
そうはいっても、素振りも満足にできない初心者に、いきなり日本刀を持たせて真剣勝負の場に出すわけにはいきません。本人は困るでしょうし、会社としてはもっと困るでしょう。「素振り道場」としての会話学校の意義はそれなりに大きいと思います。ただ、その時、誰にならうかが重要になります。
一番いいのは、言語教育のスキルを持ったネイティブに習うことです。何しろ本物ですし、言語の深さが違います。それがかなわないのであれば、自分の方法論を持った、非ネイティブの英語教育家に習うべきです。外国人が英語を学ぶ際に、どこが間違えやすいのか、ハードルはどこか、一家言を持つ人々です。
おすすめできないのは、中途半端に上手な人に習うことです。失礼ですが、メールの文面を拝見する限り、号令をかけた副工場長さんという方はこのタイプに入りそうですね。米国のビジネススクールに留学し、TOEIC
900点、だそうですが、正直、中途半端です。ビジネス交渉の経験はお持ちとしても、教育は素人でしょう。また私の経験では、TOEIC
900点など、囲碁でいえばせいぜいアマチュア初段といった程度です。TOEICは便利な尺度ですが、しょせんペーパーテストで対策も可能ですし、事実、対策本も出回っています。ネイティブ(こちらはプロの棋士だと思ってください)との差はあまりにも大きい。レベルとしてはすぐ近くに見えても、両者の間には深い谷間があって、やすやすとは超えられないのです。
というわけで、英語習得の第一の原則です:
「ネイティブに学べ。それができなければ、方法論を持つ語学教師に学べ。」
次なる原則--それは、英語という言語の位置づけについてです。まず、英語というのは、やや複雑な背景を持つ印欧語族の一つであって、たまたま現在は世界中で幅をきかせているけれども、他のさまざま言語とは優劣はあれども対等である、ということを理解してください。
複雑な背景というのは、ケルト的古層の上にゲルマン(ゴート)語の体系がのり、その上にラテン(ノルマン)語の語彙が入る、といった歴史が生んだ結果です。おかげで、同じ「海」を指す名詞がSeaで、形容詞がMarineという、素人には判じ物のような統語体系が出来上がりました(前者はゲルマン、後者はラテン語源です)。文法は接続法や格語尾が退化して、それを助動詞や前置詞・冠詞で補うという状況。しかも綴りと発音の関係もきわめて複雑、というわけで、けっして初学者にとって学びやすい言葉ではありません。
にもかかわらず英語がここまで世界に影響力を持ったのは、英語それ自身が持つ優れた性能というよりも、19世紀には英国が、20世紀には米国が圧倒的経済力と軍事力で世界を支配したからです(同じ理由で、今世紀後半には世界中の人が中国語を話すようになっているかもしれませんが)。
そして、それだけの優越性を持っていますが、英語は他の言語(例えば日本語)とは『対等』です。ちょうど、同じレースに出場する選手は、力に差はあれども対等なように。この、“優劣はあれども対等”という感覚は、英語の根底にある重要なキーでして、ビジネスの交渉の場をはじめとして、至る所に顔を出します。
対等である以上、誰もが意志を主張はできる。そこで最初から卑屈になる必要はない。だが、勝負の結果は優劣で決まる。これが英語の論理です。あらゆるものに和と序列を求めたがる日本語の感覚とは、いかに違うか、注意してください。下手な英語で主張するくらいなら、日本語で堂々と主張すればいい--そういう意見だって、ある意味成り立ちます。逆に、英語の土俵に乗る以上は、対等な相手として、容赦なく扱われる。その中間はないことに、注意してください。
第二の原則は、したがって、こうなります:
「英語は複雑な背景をもつ、込み入った体系の言語だが、他の言語と優劣はあれども対等である。」
(この項つづく)
目標、計画、ターゲット(3)-共通言語をつくろう
(2009/06/17)
日本が目指す、二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの排出削減の中期目標が先週、政府から公表された。西暦2020年には、2005年比15%減(1990年比8%減)」とすると決まったらしい。例によって、賛否両論さまざまな意見が出されている。達成可能なのかどうか、経済への影響はどうか、そもそも本当に二酸化炭素が問題なのか、等々。しかし、ニュースをみたところ、この『目標』というがどういう性格のものなのか、コミットされたものなのか(言いかえれば達成できなかったときはどう決着をつけるのか)、それとも交渉の場での最初の「出し値」にすぎないのか、といった分析は手薄に感じられた。
『目標』を与えられれば、あとは“頑張る”だけ。その目標値が達成可能なのか、また値を測るそのモノサシが本当に適切なのか、ということはすぐに置き忘れられてしまう。これが、受験勉強社会を育ってきた私たちの、共通した習性のようだ。日本人を動かすのは、ある意味で簡単なのかもしれない。モノサシをとりだして、他人や他者や他国と比べればいい。あとは自動的に走り出す。
これまで、予測、目標、計画など、いくつかの言葉をとりあげてきた。ここで、説明を少し整理しよう。
赤字の地方空港や有料道の建設は、客観的な需要予測にもとづいて決められた、とお役人たちは説明する。しかし、こうした「予測」は科学的・客観的なこじつけであって、先に政治的結論ありきではないか、とたいていの人は疑っている。
純粋に客観的な予測なんてない。
予測は、現状の観測データと、過去の実績データと、仮説(複数)から導き出される。つまり、
「予測=データ+仮説」
である。もし仮説を明確に列挙し、複数ケースを平等に並記するのなら、それは「予測」といってもいい。しかし、何かの数字を一点見積しているのなら、それはもう意志決定の入った「計画」である。
ところで、社会での活動には、一般に次の公式が成り立つといっていい。
結果(成果)=外部環境+内部努力
これは大学受験から生産・販売、そしてプロジェクトの切り盛りまで、たいていは成立する。そして、
外部環境の変動>>内部努力範囲 なら「予測」といい、
外部環境の変動<<内部努力範囲 なら「計画」という
のが普通の言葉使いだろう。しかし、両者の差は相対的なものにすぎない。
もし企業が「需要予測」という言葉を好んで使うのだとしたら、需要(販売数量)とは天から与えられるもので、営業部門の努力ではいかんともしがたい、との世界観を表現している訳である。つまり極端に言えば、営業は無能力です、と意思表明していることになる(笑)。逆に工場が今月の「生産予測は」と言ったら・・たしかに工場は無能力だ、と思われるだろう。
さて、ここで、内部努力=目標の高さに比例する、という法則(迷信?)を持ち込むから、話がややこしくなる。実現可能性はおかまいなしに目標値が設定され、その一人歩きがはじまる。仮説のない目標や計画のことを、別名、「絵に描いた餅」とよぶ。ここから生まれるのが精神主義的「号令」というやつである。
そこで、目的・ゴール・目標、という最初の回に書いた定義を思い出してほしい。およそ人間の組織は、かならず共通目的をもつ。ただしそれは、遠いところにある。おそらく抽象的で、数字では測りにくい(測れない)ものだ。一方、
「ゴール=当面、実現をめざす行為(ないし状態)」
である。じゃあ、目標とは何だったか。
「目標=そのゴール達成の成功・不成功を検証するモノサシ」
なのだ。達成のための内部努力、そして「仮説検証」のモノサシでもある。だから、客観的に測れる(検証できる)ようにする必要がある。
こう考えてみると、『今期販売目標=50億円』というような標語が、それだけではいかに無内容か、わかるだろう。「今期は製品ファミリーの充実により、既存顧客のリピート確保をめざす(ゴール)。既存の顧客ベースによる更新需要は100億円程度と推定されるから(仮説)、その50%獲得で50億円をめざす(目標)」--こう展開してみると、目標は金額自体よりも、リピート率の方が本質だとわかる。また、需要の瞬間蒸発といった、外部環境の変動による影響を除外して、自分の内部努力のレベルを検証できるのである。
また、目標と計画の区別も自明だろう。計画値は金額ではなく「品目・数量」をベースにする。それが、営業と生産と物流の「共通言語」だからだ(個別受注生産の場合などは、品目・数量の代わりに作業・期間が適当かもしれない)。ここに、努力目標やらサバ読みやらを紛れ込ませてはいけない。
この点を明確に区別するため、別の用語を用いたほうがいい。そこで『ターゲット値(ストレッチ目標値)』という言葉を提案したい。これは通常努力に加えて、さらなる改善努力を促すために設定される目標値を示すものだ。
ターゲット値は、数量や金額ベースで立ててもいいが、スループット(付加価値額)や生産性を尺度にする方がいい。こうすれば、計画と目標の二重帳簿に悩まされずにすむ。計画は100台。そのときの付加価値額の計画値は1台120万円、でも目標は150万円とする(つまり計1億5千万を売上-材料費で生み出す)、という風に。営業は計画数量を「より高く」売り、生産は計画数量を「より安く」作る。あるいは「より早く」作る。これにより付加価値生産性を上げ、生産余力を生み出すのである。
ターゲット値(付加価値額)=平均的付加価値額+改善努力のための仮説分
ターゲット値(生産性)=平均的生産性-ムダ・サバ
(言うまでもないが、欠品率だとか納期など小さい方が良い尺度の場合は、ターゲット=計画の目標値-改善努力マージン、になる)
では、営業と生産の間での計画の共有・対話はどうするのか。そのために、双方が確約可能な「基準計画」(Committed
Plan)を作るのである。
基準計画=ターゲット生産性ベースの計画+必要最小限のゆとり(自由度)
自由度は、リスクや外乱に対応するためのマネジメントの余地(Contingency
Reserve)である。これを持たないツンツルテンの計画は、予期しない出来事がちょっとでも起きると達成不能になる。だから基準計画にはつかえない。むろん、ゆとりがダブダブになっても逆に困る。だから「必要最小限のゆとり」なのである。
このことは、通信理論や情報理論を知っている人には喩えで説明した方がかえって分かりやすいかもしれない。通信符号化の手法では、まず対象の情報源から、冗長性をすべて抜き取って圧縮する。その上で、必要最小限の冗長性をあえてつけ加えることで、通信路の雑音から情報を守るのである。あるいは、在庫理論で言えば、不要な「できちゃった在庫」はすべて圧縮して、必要最小限の「バッファー在庫」だけ必要箇所に準備する、と言おうか。
こうして出来上がった基準計画は、共通言語として社内でつかえるし、かつ各部門での努力のターゲットも設定できる。計画期間が完了したら、目標と実績を比べて仮説検証もできる。こうして、意味不明な二重帳簿や混乱がなくなるはずなのである。それで、二酸化炭素15%削減というのは、どの目標なのですか、総理殿?
計画の二重帳簿はなぜ発生するか - 目標、計画、ターゲット(2)
(2009/06/09)![]()
休みをとって、愛媛から本四架橋を通って広島まで抜ける旅行をした。のんびり鉄道とバスを乗り継いでいったのだが、幸い天候に恵まれ、とくに瀬戸内の風光の美しさには感激した。青く穏やかな海の上に、大小の島が浮かび、新緑が陽光を浴びて静かに佇んでいる。さすが「しまなみ海道」と名付けられるだけあって、良い景色だった。高速バスだとあっという間に通り抜けるだけだが、それだけではもったいない場所だと思う。
この本四架橋ルートは複数の異なる構造の橋からなっていて、シビル・エンジニアリングの観点からも興味が尽きない。また、このルートを決める際のプロジェクト・マネジメントの苦労も十分想像できた。ただ、それにしても最後に広島空港に乗り継ぐまでが遠くて閉口した。あんな山の上にわざわざ空港を作るのは、まあ科学技術の勝利かもしれぬが、科学の無駄な勝利というのもあるのだな、というはなはだ失礼な感想をもった。
本四架橋や東京湾横断アクアラインが巨額の赤字を抱えているのは、よく知られた事実だ。広島空港の場合は知らぬが、最近また増え続けている地方空港(先週も静岡に開港したが)も赤字が多い。用地買収の長期化、材料費の高騰、政治の横やり等、いろいろなリスク要因はあるのだろう。だが、一番の問題として指摘され続けているのは、「事業計画の見通しがそもそも甘い」ということだ。
「地方有料道、6割が赤字 76%が需要予測下回る」という記事を、『ファイナンシャルプランナーのニュースチェック』というブログが掲載していた。「06年度の交通量が計画に達しなかったのは125路線中95路線。50%に満たなかったのは28路線に及んだ」という。中でもワースト3位の長良川右岸有料道路、常陸那珂有料道路、福島空港道路は、実際の交通量が計画の20%にも満たない。こうなると、そもそも「計画」って何なの? という当然の疑問がわいてくる。
「明日の天気は晴れを計画します」と気象庁が言ったら、可笑しいと誰もが思うだろう。「今日の交通事故数は、計画では2件です」と警視庁は言うまい。カツオ漁師は明日の水揚げ量を計画するだろうか。でも漁師だって、交通警官だって、何らかの見通しの上で毎日の仕事の「計画」を立てているのだ。
「計画=予測+意志決定」である、という式を、前にもこのサイトで書いた。今回は、この式をもう少し因数分解してみたい。まず、「予測」の方であるが、そもそも人間であるかぎり完全な予測というものは不可能である。そこで、さまざまな前提条件と近似を積み上げて、数値予測を行うことになる。それは、単に一つの部品を旋盤で加工するための所要時間、といった単純な予測でさえ、そうなのだ。自社内の行為でさえ、いくつかの条件(平均的な習熟度の作業員がやって、材料鋳物には不良が無く、かつ標準加工手順にしたがえば、etc.)を積み上げて、やっと「40分かかるでしょう」という答えが出てくる。
よく、「MRPは実現不可能な生産計画を作ってしまうが、APSは実行可能な正確なスケジュールを生成してくれる」というようなことを主張する人もいるが、これは正しくない。APSの出す答えもまた、スケジュールの一種の近似にすぎないからだ。単に、予測精度の違いということなのである。
ましてこれが、自分でコントロールしがたい、外部環境に大きく左右される現象ならばなおさらである。需要予測がその代表例だ。「需要計画」などと言う人間が少ないのは、自分の努力によって制御しがたい事象だと、皆が認識している(かつての共産主義国家での計画経済は別だが)からだろう。
そして、こうした外部事象の予測においては、必ず前提条件を明らかにした上で、複数の前提での予測結果を並列に記述すべきなのである。これを「感度解析」とか「ケーススタディ」と呼ぶのはご存じだろう。前提条件はいろいろな仮定の仕方がある。そこで、こういう前提なら100だが、ああいう仮定をおけば120、という風に数字を並記するのが、由緒正しい『予測』の仕事のやり方なのである。
では、上の式における「意志決定」とはどういう行為か? それは、この複数の仮定を比較し、評価した上で、その中で一番適切なものを選択し、これを「今回の計画における仮説」と宣言する行為なのである。繰り返すが、計画における意志決定とは、仮説を選び取ることに他ならない。先のことは分からない。だから『仮説』なのである(「仮説検証のトレーニング」 2004/11/06参照)。前期はA製品が低調だった、しかし東アジアの需要動向を見ていると、今年前半には需要は底を打つ、だからAラインは生産余力を残しておいた方がいい・・こうした決定が、「仮説を選び取る」意志決定なのである。
仮説である以上、あたらない可能性もある。“はずれるかもしれない仮説に賭けるのか! それなら確実な戦略を選ぶべきだ”という主張は、一見もっともだが、実は愚かだ。「確実な」将来というのは、あり得ない。確実な戦略といわれるものの多くは、じつは「過去しばらくあたっていただけの戦略」にすぎない。もしかするとそれは、“変化を拒絶する”という最低の戦略なのかもしれない。
さて、現実の企業組織において困ることは、この「仮説」の好みが、部署により立場によって異なることだ。営業部は「もっと低価格なB製品なら多少売れるかもしれない」、企画部は「新しい技術をいれた新製品Cならヒットの可能性がある」、製造部は「製品Aが一番原価低減の余地があるから良いのではないか」・・とバラバラになるのだ。そしてお互いに、自分の好みの仮説に基づいて予測を立てて行動する。“営業は10万個売れると言っている。でもあれは予測ではなく努力目標にすぎない。それを信じて10万個分の部品を手配したら、在庫増で上から怒られる。だったら5万個を仕入れて後は様子を見よう・・”こうして計画の二重帳簿がはじまるのだ。
私の見聞きしてきた経験の範囲から言うと、競争力の高い(したたかな)企業は、皆が同じ一つの仮説を共有して動いている。しかし、そうではない大多数の「普通の企業」は、その規模の大小にかかわらず、皆がバラバラの仮説で動いているのである。いや、そういった企業では、仮説が仮説と意識されないまま、各人の「経験知」として、真実であるかのように流通している。かくて、営業部が立てた販売計画とは別の数字を元に、工場が生産計画を立てる、という(しばしば見かける)事態が出現する。あるいは、プロジェクト的なビジネスにおいても、営業とプロマネと設計技術と品質管理が、互いに別々の思惑で動く状態を生じさせるのである。
このようなバラバラな状態をただす方法は何か。それは、一見逆説的に聞こえるかもしれないが、意図的に計画の中に「幅」と「目標」を持ち込むことなのである。
(この項もう一度続く)
先日、機会があって東大工学部の学生たちにプロジェクト・マネジメントの講義をした。わずか2コマ・計3時間の講義でどれだけのことを伝えられたかは定かではないが、アンケートを見る限り、少なくとも「マネジメントには技術(テクノロジー)があり、理工学的なアプローチが可能である」という事実は、興味を持って理解してくれたようだ。WBSだとかクリティカル・パスだとか、ごく初歩的なことがらを演習してみて、それを強く感じたらしい。
このことは、あの大学に経営工学や管理工学といった理系のマネジメント学科が存在しないことを思い合わせると、とくに貴重なことのように思われる。東大の理工系を卒業する人は、マネジメントについて何も教わらぬまま社会に出て、人に指示を出す職業に就いてしまう可能性が高いからだ。日本のいろいろな組織が、確とした指針も方法論もないまま、リーダー層のセンスや勘や経験だけで動かされることになる一因かもしれぬ。
それにしても、学生さんたちの回答を見ていて気がついたことが一つある。それは、「目標」というものに関する誤解、ないし理解不足である。この講義で私は、“自分が現在かかわっているプロジェクト(ないし近い将来かかわるであろうプロジェクト)を例にとり、その『使命(ゴール)』と『目的』と『目標』を言葉で書きなさい”という演習を出してみた。ミッション・プロファイリングの初歩である。
ゴールと目的と目標は、混同して使われることが多い。そこで、あらかじめ講義の中で、次のように説明した。(1)ゴールはそれを達成すればプロジェクトを終えることのできる完了条件である。(2)目的はそのプロジェクトを発案し進めるに至った背景ないし意図であり、ふつうゴールより広い視野でとらえる。(3)目標はそのプロジェクトが成功したかどうかを判定するためのモノサシである。目的と目標はまぎらわしい言葉だが、「今年の販売目標は100億円」とは言っても、「今年の販売目的は100億円」などとは言わないことを思えば、違いを理解できるだろう。
ここまで説明してあるのだから、この演習問題はじつに簡単なはずである。たとえば「卒論研究」というプロジェクトをとったとしよう。その使命(ゴール)は「○○をテーマとした卒業論文を書いて提出する」であり、目的には「○○を研究して明らかにすること、ならびに無事に卒業すること」があげられるはずだ。そのための目標値としては、「少なくとも卒論発表で及第点をとる(ような内容にしあげる)」ことをあげなくてはならない。
ところが不思議なことに、『目標』のところに「実験器具の使い方を習得すること」とか「○○理論の文献調査で理解を深めること」などと書いてくる人がいる。これらは、すべて目的を達成するための手段・道具でしかない。どうも、手段と目標を混同しているらしいのだ。いかに実験器具を操るのが上達しようが、発表審査で落第したら、その卒論プロジェクトは失敗である。
しかし、おかしなことに、企業人を相手に同じ演習をやっても、同様に目標と手段を混同した答えが、しばしば返ってくる。人も知る立派な企業のエリート社員たちが、「目標」を正しく立てられないのだ。これはいったい、どうした現象なのだろうか?
もう一度書くが、目標とは、そのプロジェクトが成功したかどうかを判定するための、客観的に検証可能な基準である。なぜ検証するのか? それは、失敗であれ成功であれ、そこから、次のプロジェクトの成功のために「学び」を汲み上げるためだ。これは自分で経験から学び取り、自分で改善するための契機なのである。だから、目標は自分で設定しなければダメなのだ。それも、努力すれば実現できる程度に「実行可能な」ターゲットの目標値を。また主観的・定性的な目標では不十分で、はっきり誰でも測れて合意できるものでなければ役に立たない。
プロジェクトとかプログラムといった営為では、最初の目的・目標設定が非常に大事である。こんなことはマネジメントのはじめの一歩で、今更言うまでもないはずだ。しかし、どうやら「先進国に追いつけ・追い越せ」で長らくやってきた我々の社会は、この目標の自己設定がへたらしい。目標は誰かから与えられるもので、自分で考えるものではないのだ。大学に入るのは学んで賢くなるため(=目的)だったはずなのに、いつのまにか入学が自己目的化し、入試の点数で何点以上という目標がふって降りてくる。本当にこの試験勉強で自分が賢くなれるのかは、もう問わない。
「ERP導入プロジェクトをスタートさせます。目的は基幹システムの近代化で、ゴールは会計・販売・物流機能の全社展開です。」--ここまではたいていの会社できちんと宣言する。しかし、目標は? 売上増加、あるいは在庫削減、あるいはシステム運営費の削減? それが達成できたかどうか、いつ誰が判定するのか。ほんとうにERPを入れたら売上は伸びるのか? 売上増を達成できなかったら、それをどう教訓として活かすのか。こうした点は曖昧なまま、いつのまにかプロジェクトは終わってしまい、疲労困憊したチームメンバーと、現場のぶつぶついう不満やつぶやきが残るだけ、というケースを見かけないだろうか。
・・と、本当はここまでが話の導入部分で、これから『計画』と目標の二重帳簿について議論するつもりだった。だが、いつものくせで、少し長くなりすぎた。この問題については、また稿をあらためて書くことにしよう。
以前、丸谷才一のエッセイを読んでいたら、「順調だった議論がこんぐらがるのは、たいてい比喩のところからだ」と書いてあるのをみて、なるほど、と思った。他人に論点をわからせようとするとき、われわれはよく比喩を使う。たとえば、“在庫とは時間のかんづめのようなものだ”とか、“(海外からの)技術導入は麻薬のようなものだ”といった言い方である。前者は、在庫物品があらかじめ進められた調達/製造工程の結果であることを言い表しているし、後者は、技術導入の成果は翌日からでもすぐ商品になるが、自分の能力的成長が得にくくずっと依存し続けることになる事情を示している。しかし、こうした喩えはインパクトが強いが、もとの事象をおおざっぱに表しているだけなので、どうしても異論が出やすいのである。議論のさなかに比喩を使うときは、かなり注意して用いる必要がある。
もうひとつ議論を混乱させやすい因子としてあげられるのは、形容詞である。「大きい」「小さい」「高い」「低い」といった形容詞をわれわれはしばしば使うが、これが結構、異論の元となりやすい。というのは、こうした形容詞はその裏側に評価というものがはり付いているからだ。「在庫が小さい」といえばポジティブで、「製造のコストが高い」といえばネガティブに聞こえる。そこで、異論を持つ人からすぐ、“いや、一概に小さいとは言えない”とか“営業経費だって小さくない”と反論が来る、という次第である。
ところで、形容詞による議論の混乱は、簡単な解決方法がある。それは、「大きい」「小さい」といった言葉の代わりに、具体的な数字でいってみることである。「在庫は1.2億円分ある」とか、「製造のコストは5年前に比べて40%上がっている」と言えばいい。そうすると、議論は1.2億円という数字がどの程度正確か、またその数字をどう評価するか、という方向に進んでいく。事実認識の問題と価値評価の問題を分けて考えることができ、議論のクラリティ(明晰度)が上がるのである。
そういえば、私は若い頃、先輩から「エンジニアは数字で話せ」と教えられた経験がある。技術屋だったら、多い・少ないの『言葉』ではなく、10%なのか90%なのか数字で示せ、という訳である。逆に、数字に落とし込めない議論は、どこかにゴマカシがあるかもしれない、とさえ感じるようになった。議論する前に、まず事実を見ろ。事態の評価に飛びつく前に、まず事態を客観的に把握しろ--先輩の教えは、そういうことだった。
前回、『データを情報に変える』(「考えるヒント」2009/02/14)で、「情報とは、人間にとって意味をもたらすもので、ふつうは言語のかたちをとっている」と書いた。「データとは中立なもので、それ自体は価値を持たない」とも。つまり、先輩の教えとは、情報レベルでのやりとりで混線したくなければ、まず情報をデータに落とし込め、といいかえられるのかもしれない。この方が、伝達や再利用での可能性が広がるからである。
ここでいう「データ」とは、別に「電子データ」の意味ではないことに注意してほしい。客観的で定型化されている数字や文字の並び--それがデータである。だから、パソコンの中に、ワープロのファイルが山ほどちらばっているけれど、いちいち中身を開けてみないと何がなんだか分からない、といった状態はデータの用をなさない。効率よく探し出せなければデータとはいえないからだ。
われわれはオフィスでメールや電話のかたちで、日々かなり大量の情報のやりとりをしている。そして、そうした情報は基本的に非定型である。一方、オフィスワークは誰がやっても合格点のレベルで仕事が動くよう、(判断を含めて)プロセスの標準化が求められる。「需要が大きそうだと課長さんが判断したから在庫を増やしました」というレベルでは、組織としての一貫性は保てない。「この先3ヶ月間で必要な在庫費用は60万円だが、欠品の機会損失は100万円以上になりそうなので在庫しました」というレベルの判断が望ましい。
この「判断の標準化」、あるいは「判断の見える化」に必要なことが、数字とデータにもとづく判断基準なのである。そのためには、人間が発する非定型的な意味情報を、いったん定型化してデータに落とし込み、蓄積したり集計したりする作業が必要になる。そして、そもそもITとは、そのためのツールであるはずだった。情報をデータの形にして機械に処理させ、機械のもつデータから情報を取り出す。このサイクルをうまくつくることこそ、IT利用の最大の勘どころなのだ。
たとえば請求書を手書きの伝票で送るのと、ワープロの手紙で「二百万円おしはらいください」と書いて送るのと、どっちがIT化に近いだろうか? ワープロの方だと思う素人は、少なくあるまい。ところがIT屋の目から見ると、手書き伝票の方がずっとデータに落とし込みやすい。形式が完全に決まっているからだ。宛先があり、日にちがあり、品目と数量と金額が一行ごとにあって、最後に合計と振込先がある。どこをみればどの項目か迷うことがない。他方、ワープロのファイルを開いて、文章の中から金額をつかまえるのは容易ではない。
ごく単純で機械的な作業で処理できるようなものを定型的という。非定型的な情報は、高度な知的判断を必要とする。ワープロのファイルは非定型だからデータではないが、手書き伝票は定型化されているからデータである。データに落とし込むためには誰かがはじめにその形式をうまく考えて定義してやる必要がある。その形式化をおろそかにすると、データとしての取扱いの難しい、非定型な情報ばかりが行き交うことになる。
データから情報をくみ上げ、また情報をデータに落とし込むサイクルを構築することこそITの能力であり、こうしたことを教えることこそ、真の情報教育だと思う。にもかかわらず、情報とデータに関する基本的理解が足りないまま、情報技術をほんの表層だけつかっている状態がいかに多いことか。お金を計算機にかけながら、実際にはその半分の価値も引き出していない「IT未満」型利用者が多すぎる。
IT未満な人たちは、ワープロや表計算なんかのITツールを、もっぱら『清書用の道具』としてとらえる傾向が強い。だから帳票類を電子化するときも、罫線や図形を神業的に駆使して、紙と見た目そっくりにすることに命をかける。その結果、たいていは入力も面倒、データとしての再利用にもひどく不便、なものになってしまう。それどころか、管理職経由で電子メールで送ればすむものを、わざわざプリントアウトして判子をつくことを強制したりする。こういう病はあちこちではびこっている。
各人のスキルないし職人芸的判断に任せる部分が大きく、仕事の流れが定型化していないところでは、みなが高度な知的判断をしなければならなくなる。日本企業がこうした部分を放置したまま、目先の「合理化」のために人減らしをしているうちに、後ろから中進国に追いつかれ追い抜かれたりする状態にならないことを、私は切に願うのである。
ここに一つの数表がある。最近の企業業績に関するデータをもとに作成したものの一部だ。類似した業種の会社7社を選んで、並べてある。
売上高
従業員数
粗付加価値額
付加価値生産性
労働装備率
企業1
36,499
2,039
25,859
12.68
12.6
企業2
709,554
5,661
184,161
32.53
29.5
企業3
87,752
2,031
26,411
13.00
12.2
企業4
282,091
3,358
64,769
19.29
23.0
企業5
257,471
2,509
29,808
11.88
17.1
企業6
80,080
2,170
46,328
21.35
16.4
企業7
194,356
3,343
76,324
22.83
28.2
これをみて、どのようなことを感じられるだろうか。たぶん、なんだか数字が並んでいるだけで、何も感じようがない、と思われるだろう。
それでは、この中の二つの項目を選んで、グラフにしたら、どうだろうか。
これをみると、どうやら企業の生産性(付加価値生産性)と、その企業の労働装備率との間には、一種の相関関係があるらしい、ということに気づくだろう。労働装備率は従業員一人あたりの固定資産額で、製造業の場合は主に工場設備に左右される。ここから、人を増やさずに生産性を上げたければ、工場の近代化投資が必要らしい、という仮説が浮かんでくる。
とはいえ、今回のテーマは工場の話ではない。上に上げた表は、定型化された数値や文字の並び、すなわち「データ」である。では、グラフの方はどうか? こちらもデータである。ただ、そこから、“生産性と労働装備率とは関係がありそうだ”という「情報」が浮かび上がってくる。データから情報を組み上げるプロセス、これは人間の心が持つ「気づき」という知的な働きによるものだ。コンピュータは、人間に情報をもたらしてくれたりはしない。
以前、出版社の人に、ITの本質を理解している人を見分ける方法はあるかときかれたとき、とっさに私はこう答えていた。『データと情報はどこがちがうか?』と訊ねてみてください、と。なぜなら、ITをよく分かっていると人とは、データと情報のサイクルを意識して活用できる人に他ならないからだ。
たいていの人は「データ」と「情報」という二つの言葉を、あまり区別せずにつかってる。専門書も、あいまいな場合がある。しかし、ITを理解する上では、この両者ははっきりと区別する必要がある。
「情報」とは、人間にとって意味をもたらすもので、ふつうは言語のかたちをとっている。逆にいえば、すぐに意味をくみ取れないものは、たとえ言葉で書かれていても、情報の役割をはたさない。
一方、「データ」とは何か。データとは、数字や文字の形式化・定型化された並びのことだ。「表のようにきちんと並んだ」と理解してもいい。たとえば、新聞の株式欄はデータである。会社名と、株価の数字が整然と表になって並んでいる。駅の時刻表や電話帳もデータだ。データはべつに数字が並んでいる必要はない。文字だけでもデータだから、住所録や学校の卒業名簿だってデータである。
データというものは、必ずしもコンピュータの中に格納されていなくてもいい。「あの野球監督はデータにもとづいて作戦を立てる」といったとき、そのデータは過去のスコアブックの集積を指しているので、それがパソコンに入っているかどうかは本質ではない。その監督が単なる人情や勘だけで指示を出しているわけではない、ということをいっているのだから。
いや、新聞の株式欄は『情報』じゃないか、という反論もあるかもしれない。ある株が上がったか下がったか、どの会社が今、注目株か。これはみな『意味』そのものだから、さっきの定義にしたがえばデータではなくて情報ではないのか? --とはいえ、株式欄の数字の羅列から意味をくみ出すのは、人間の側の頭脳や精神の働きである。
最初にあげた数表とグラフを思い出してほしい。図を見ると、労働装備率が高い企業ほど付加価値生産性も大きいことが理解される。データの中にある関係性(これを共分散構造と言ってもいい)を見いだし、人はそこに意味を発見する。しかし、コンピュータは、表の形になっていようが、グラフの形で表現されていようが、そこから自動的に意味をくみ取るようなまねはできない。
つまり、「データ」とは中立な(いいかえれば無味乾燥な)もので、そこから意味を引きだして「情報」にするのは人間の認識力なのである。だから、データそれ自体は価値を持たないが、それを利用できる人にとっては潜在的価値がある。データとは、見かけは荒れ地だが地下に石油の鉱脈が眠っているかもしれない土地のようなものだ。
もう一つ、データと情報には重要な違いがある。コンピュータの中に格納して処理できるのはデータだけなのである。機械にできるのは、形式化され定型化された数字や文字の並びを、あれこれと加工することに限られる。「IT=情報技術」という名称とは裏腹に、コンピュータは情報は扱えない。なぜなら、情報には決まった形がないからである。
物流の世界にたとえれば、コンピュータというのはデータという荷物の運送業者だ。データを受け取って、車に積んで、集積所にはこんだり車につみかえたりしたりして、相手先に届ける。だれかにものを送りたいときには、それが本であれ服であれ花束であれ、とにかく何かの箱に入れて宅配業者に渡すだろう。ばらばらで形の定まらないものを渡されても業者は困ってしまう。機械的にハンドリングできないからだ。また逆に、運送業者にとって、箱の中に何が入っているかは興味がない。箱の中身に人がどういう意味を託そうが、それは彼らにはあずかり知らぬこと、知りようのないことだ。
ではなぜ、「IT=情報技術」などという概念が生まれるのか? それは、情報という上層のレイヤーとデータという下層のレイヤーをとりもつための技術だからだ。情報という大事な品物を、データという形の決まった箱に入れて処理しやすくし、また逆にデータの箱の中から、うまく情報の品物を引きだすことで、
→→情報→→
↑ ↓
←←データ←
という円環をつくってまわしていく。この、“データと情報のサイクルを回す”ということが、IT利用スキルの本質なのだと、私は考えている。